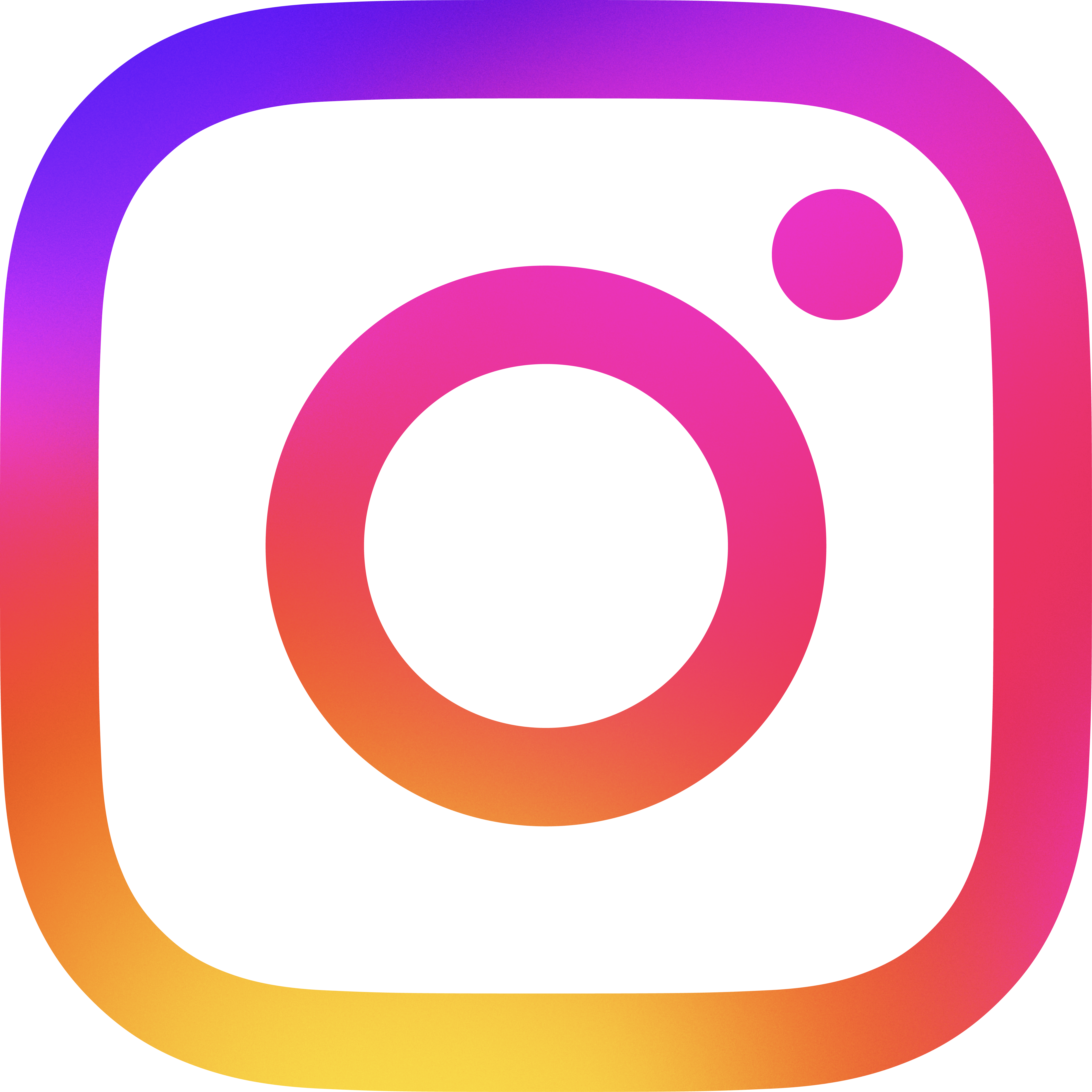大人のADHDの特徴って?特性との向き合い方について調査

仕事でケアレスミスが目立つ、人間関係を良好に築けない、片づけが苦手…このようなことで悩んでいませんか。これらのことを「自分の努力が足りないせいだ」と言う風に自分を責める前に、ADHDの可能性を疑ってみる価値はありそうです。
この記事では、大人のADHDの特徴や特性との向き合い方について調査したことを分かりやすくまとめています。
※筆者は医師ではありません。この記事はインターネット上で筆者が調べたものを筆者の言葉で執筆している物なので必ずしも正しいとは限りません。ADHDについて分からないことがある場合は、必ず医師に相談するようにしてください。
ADHDとは何か?大人のADHDという言葉ができた背景
ADHDってどんなもの?どうして「大人のADHD」という言葉をよく耳にするの?そんな疑問にお答えするべく、ADHDについて基本的な説明をするとともに「大人のADHD」という言葉ができた背景について解説します。
ADHDとは
ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略で、日本語に訳すと「注意欠如多動症」となります。ADHDは発達障害の一つで、「脳の特性」であり「病気」ではありません。
ADHDには大きく分けて「不注意」と「多動性・衝動性」の2つの特性があります。
参照:大人の注意欠如多動症 (ADHD)とは – 武田薬品工業 | 「大人の発達障害ナビ」
大人のADHDという言葉ができた背景
大人のADHDという言葉をよく耳にするという人は少なくないでしょう。しかし、ADHDは大人になってから突然発症することはありません。
ではなぜ、大人になってからADHDと診断される人が多く、「大人のADHD」という言葉が存在するようになったのでしょうか。
●子どもの時は気づかれにくい
子どもの頃は、ADHDでもその特性が「おっちょこちょい」「元気な子」と判断され、ADHDであることを見過ごされやすいという傾向があります。
●大人になると特性が表面化する
子どもの頃は気づかれなくても、社会に出ると責任が重くなり、タスク管理を求められる場面が多くなります。その結果、ADHDの「不注意」「多動性・衝動性」の特性が表面化し、周りに迷惑をかけてしまうこともあると考えられます。
そのことから「生きづらさ」を感じ、受診して初めて自分が「大人のADHD」であることが分かったというケースも少なくないでしょう。
●インターネットの普及でADHDに対する知識や理解が深まる
また、インターネットでADHDについての様々な知識を得られるようになり、受診する機会が増えたことで「大人のADHD」と診断される人が多くなったということも背景の一つとして挙げられます。
参照:【医師監修】増加傾向にある大人の発達障害(ADHD・ASD)その分類と特性をわかりやすく解説|オンラインカウンセリング「mezzanine(メザニン)」
大人のADHDの特徴は?特に多く見られる困りごとはこれ!
大人のADHDの特徴にはどんなものがあるのでしょうか。また、大人のADHDの方に特に多く見られる困りごとには何があるのでしょうか。
ここでは、大人のADHDの特徴と困りごとについて解説していきます。
大人のADHDの特徴
大人のADHDの特徴を、前述した2つの特性に分けて説明していきます。
●不注意
- 集中し続けることが難しく、作業においてミスをしやすい
- 物をなくしやすい
- 忘れ物が多い
- 約束を忘れる
- 計画や予定を立てられない
- 片づけが苦手
●多動性・衝動性
- 落ち着きがなく、じっとしていられない
- 順番を待つことが難しい
- 一方的なおしゃべりをする
- 衝動的な感情や行動を抑えることが難しい
- 金銭管理が苦手
このように、ADHDには多くの特徴がありますが、必ずこれら全てが全てのADHDの人に当てはまるというわけではありません。人によっては不注意の特徴が大きく出たり多動性・衝動性の特徴が大きく出たりと個人差があるようです。
大人のADHDに多く見られる困りごと
上記のADHDの特徴から発展して、そこから引き起こされる困りごとについて大人のADHDの方に特に多く見られるものを挙げていきます。
●人間関係のトラブル
衝動的に発言や行動をすることが原因で、周りの人と衝突したり誤解されたりといったことがあります。
また、会話のテンポを合わせられなかったり待ち合わせで遅刻を繰り返したりといったことが重なると、時には孤立してしまうこともあります。
●仕事がうまくいかない
書類を紛失したり、大事な予定を忘れてしまったりとケアレスミスが続くことがあります。複数の作業を同時に依頼されるとパニックになることもあります。
そのようなことが重なると、上司や同僚との信頼関係がうまく築けなくなるという可能性もあり、加えて自分が仕事に対する意欲を無くすなど「生きづらさ」を感じることがあります。
●家事がうまくできない
片づけ・掃除などを途中で放棄してしまうことがあります。その結果、部屋がなかなか片付かないということがあります。
また、時間の管理が苦手なので家事のスケジュールが組めず、買い物を忘れてしまうなど生活に支障が出ることがあります。
これらの困りごとにより、ADHDの方の中には自分の特性を認めることができずに過剰に自分を責めてしまう方もいるので、特性に対する対処の仕方を知ることが重要になってきます。
ADHDとの向き合い方って?必要なら専門家への相談も◎
ADHDの特性は様々な困りごとや生きづらさを生み出しますが、それを軽減する方法も確かに存在します。
ここでは、ADHDの特性との向き合い方についてや、周りの人がADHDの方をどのようにサポートすれば良いのかについて解説していきます。
ADHDの特性との向き合い方3つ
●環境調整
環境調整とは、自分のADHDの特性(苦手なことだけではなく得意なことも含む)をよく理解し、苦手分野を補うことを目的として生活環境を見直す方法を指します。
特に仕事の場面においては、上司や同僚とうまく折り合えるように自分の特性について相談し配慮をお願いしたり、仕事をする上で自分なりに工夫を取り入れたりすると職場における一般的な仕事の在り方に近づけることがあります。
<環境調整の例>
・仕事の納期や会議の日時を忘れてしまう場合
スマホのリマインダーやカレンダー、アラーム機能などを使う。上司や同僚に、約束の日時の前には確認のため声をかけてもらえるようお願いする。など
・仕事に集中できない・気が散ってしまう場合
隣の席との間に仕切り板を立てる。耳栓を使う。スマホは電源を切ってカバンにしまう。机の上に仕事と関係のないものを置かない。など
・整理整頓が苦手で、ものを片づけられない場合
そこに入っている物、置いてある物の絵や写真を分かるように貼っておく。など
●認知行動療法
認知行動療法とは、ADHD特有の考え方のクセに気づき、自分自身に対する理解を深めることを目的とした心理療法のことを指します。認知行動療法を通して得た気づきにより自分の行動パターンを少しずつ変えていくことで、社会に適応できる方向へ繋げていきます。
●薬物療法
ADHDの症状を改善するために、薬を服用するという選択肢もあります。しかし、薬物療法のデメリットとして、全ての人に効果が見られるとは言い切れないこと、副作用のリスクがあることなどが挙げられるので、専門家へ相談をしてどうするのかを決めましょう。
これら3つの向き合い方にはそれぞれ考え方の違いがあります。例えば環境調整は「周りを自分に合わせる」考え方によるものですし、認知行動療法や薬物療法は「自分を周りに合わせる」考え方から生まれたものです。どれを選ぶのか判断がつかない場合は、精神科・心療内科などの専門家に相談するのが良いでしょう。
周りの人がサポートできること
ADHDの人が身近にいる場合、周りの人はその人がどんなことで困っているのかを理解し、どうしたらその困りごとが軽減されるのかを一緒に考え、実践することが大切になってきます。
例えば職場では次のようなサポートをするとADHDの方に喜ばれるのではないかと考えられます。
- 指示はなるべく具体的に、口頭ではなく文書にして伝えるようにする。
- 大声を出さない。威圧的な態度で接しない。
- 多くのことを一度に頼まないようにする。
家庭では、次のようなサポート方法が考えられます。
- 一日のスケジュールや持ち物について一緒に確認する。
- 物をなくさないように、保管場所を一緒に決める。
- 視覚的に確認できるように、忘れないでほしいことをメモや付箋に書いて貼る。
根本的な考え方として、その人がADHDであること以前にその人のことをあるがまま受け入れることが大切です。初めのうちは折り合えなかったとしても、お互いが歩み寄ればいつの日か分かり合い、一緒に仕事をしたり楽しい時間を過ごしたりできる時が来ると信じたいものです。
ADHDの「生きづらさ」を理解して自分らしく生きよう
ADHDの方は、いま、この日本で生活している時は困りごとが多くあって「生きづらさ」を感じることも多々あるかもしれません。でもそれは、ADHDの方の人間性が全否定されるということではありません。周りの「やり方」や「ルール」が合わないだけで、それを取っ払えばADHDの特性に関係なく一人の人間ということに変わりはないのです。
ADHDの方の「生きづらさ」はどんな時に感じるのか?どのような形をしているのか?それを理解することで、対処の仕方も分かってきます。自分らしく毎日を過ごしましょう。