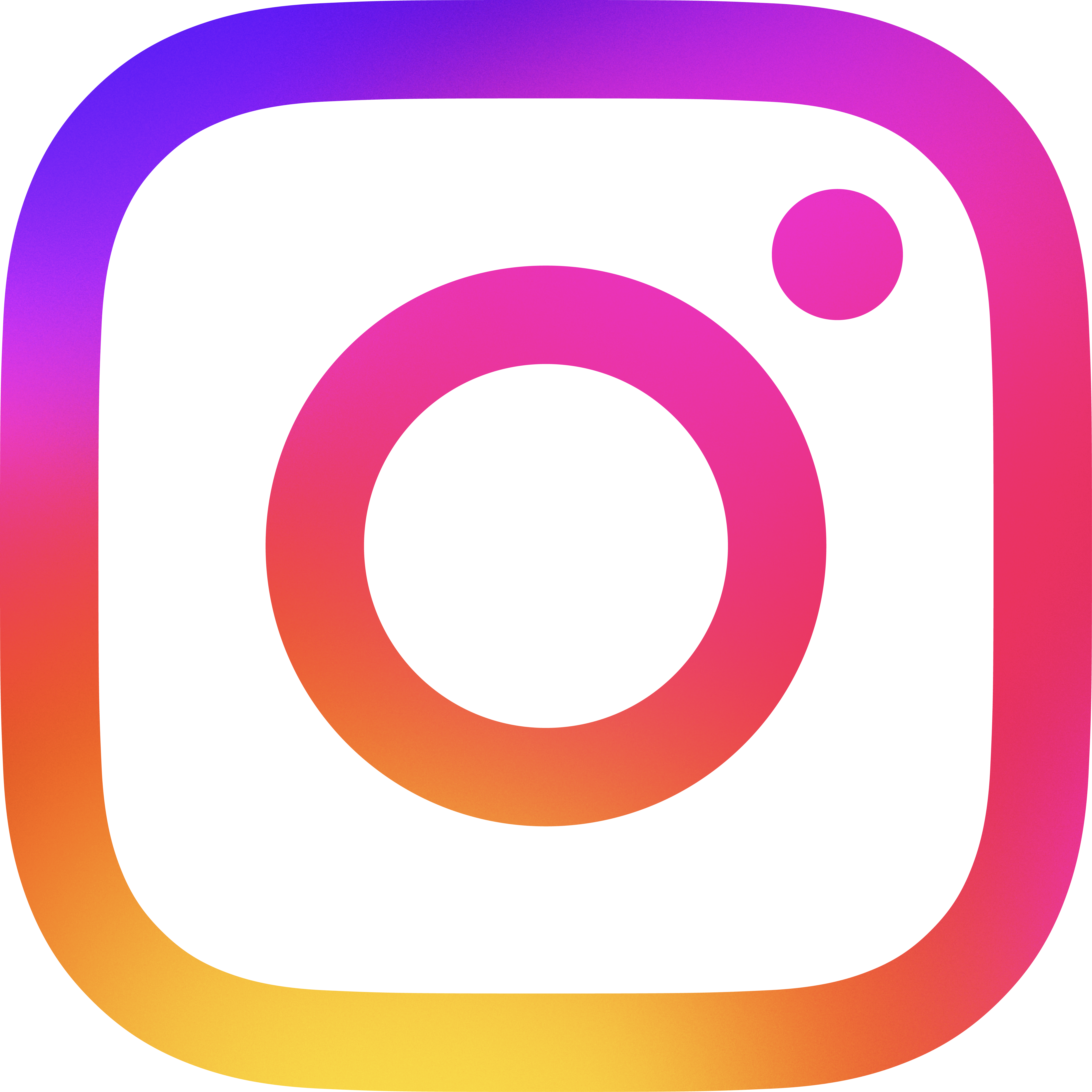夏の風物詩・お盆は何をする?歴史・イベント・迎え方などを紹介!

日本では古くから時期ごとの行事が多数行われており、現在まで残っているものも少なくありません。夏の大きな行事として「お盆」が挙げられます。この世に帰ってくる先祖の霊を迎える行事で、家で過ごしたり旅行を楽しんだりとさまざまな形で活用されます。この記事ではお盆の歴史やイベント、迎える流れなどを紹介します。
お盆とは
お盆は日本全国で古くから行われている夏の恒例行事です。過去に亡くなった先祖の霊がこの世に帰ってきて親族とひとときを過ごすとされており、先祖ヘの感謝や成仏の祈りなどを込めて行われます。親族が集まってお墓参りに行ったり会食したりして過ごすため、多くの人が移動する行楽シーズンでもあります。お盆の時期に行われるイベントも少なくありません。お盆の歴史やイベント、関連する要素などを以下で紹介します。
起源
お盆は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という仏教の行事が略された名前で、さらに元を辿るとサンスクリット語の「ウランバナ」に行きつきます。ウランバナは「逆さ吊りの苦しみ」という意味があり、釈迦の弟子であった目連とその母にまつわる物語に由来します。
目連の母は息子を溺愛するあまり周囲の不幸に関心を持たず、死後に地獄で逆さ吊りの罰を受けていました。母を哀れんだ目連は釈迦に相談して、「夏の修行を終える7月15日に供養しなさい」と助言をもらいました。目連が釈迦の助言に従ったところ、目連の母は救われて無事往生できたという物語です。
ウランバナの物語は飛鳥時代に日本まで伝わり、最初は朝廷で先祖を供養する行事として取り入れられました。民間に広く普及したのは江戸時代とされます。ロウソクの生産量増加やコスト低下によって庶民でも入手しやすくなり、多くの人が7月15日前後に先祖の供養を行うようになりました。
参照:「お盆」の原点は古代インドから始まっている | ニッポン放送
お盆とは?意味や由来、期間について | お仏壇のはせがわ
お盆の由来って? | よりそうお葬式
地域によって時期が異なる理由
現代において「お盆」とされる時期は地域によって差異があります。全国的には8月中旬に行う「8月盆」が主流です。しかし、東京・神奈川・静岡など一部地域では7月中旬にお盆を迎える「7月盆」が採用されています。また、沖縄や奄美などでは「旧暦盆」として、毎年異なる時期がお盆とされています。
お盆を迎える時期の違いは明治時代の改暦に由来します。明治初期に政府が近代化の一環として西洋由来の太陽暦を導入して、旧暦の明治5年12月3日が新暦の明治6年1月1日になりました。約1ヶ月早く新年を迎える形になり、お盆を含む毎年の恒例行事も開催時期にズレが生じました。政府の目が届きやすい都市部ではお盆の時期も新暦基準に変更された一方、多くの地域では従来どおり旧暦基準でお盆を迎えました。その後徐々に時期が固まっていき、旧暦の7月15日に近い新暦の8月15日前後がお盆として定着しました。沖縄や奄美などは現代でも旧暦に沿ってお盆の時期を決めており、新暦とのズレから毎年異なる時期にお盆を迎えます。
参照:明治の改暦 | 国立国会図書館
地域によってお盆の期間が異なる理由 | お仏壇のはせがわ
7月盆、8月盆、旧暦盆について | eflora
地域によるお盆の時期は? | 小さなお葬式
お盆に行われるイベント
お盆には古くから全国各地でさまざまなイベントが催されており、現代でも多くが開催され続けています。全国の主なお盆のイベントとして以下のものが挙げられます。
・盆踊り
全国で広く行われる一般的なお盆のイベントです。大勢が広場に集まり、笛や太鼓の音色にあわせて踊ります。地域によってバリエーションも多く、種類によっては数百年の歴史を持っている場合もあります。
・阿波おどり
主に徳島市で行われる有名なイベントです。400年以上の歴史があるとされており、地域の盆踊りが元になったという説も存在します。毎年お盆の時期に行われて、国内外から非常に多くの参加者・見学者が訪れます。
・エイサー
沖縄県内で行われる盆踊りの一種です。起源ははっきりしていませんが、400~500年前に生まれたという説も存在します。旧暦のお盆にあわせて各地で開催されて、特に「沖縄全島エイサーまつり」ではバリエーション豊かなエイサーを観られます。
・精霊流し
主に長崎市で行われる伝統行事です。竹や板などで作られた大きな船を曳きながら、夜の街なかを練り歩きます。故人を追悼する行事ですが、「ドーイドーイ」というかけ声や爆竹などの音で非常ににぎやかな雰囲気があります。
・五山送り火
京都市で行われる有名なイベントです。お盆の終わりに市内5ヶ所の山で文字や絵の形に篝火を焚きます。左京区如意ヶ嶽の「大文字送り火」が特に有名で、始まった時期には江戸時代や室町時代などさまざまな説があります。
参照:盆踊りについて | 日本盆踊り協会
阿波おどり | 阿波おどり未来へつなぐ実行委員会
エイサーとは | 沖縄全島エイサーまつり
精霊流し | 長崎市観光公式サイト
京都五山送り火とは | 京都五山送り火連合会
精霊馬
お盆の時期にはさまざまな飾りやお供え物が用いられますが、特徴的なものとして「精霊馬(しょうりょううま)」が挙げられます。ナスとキュウリに箸や爪楊枝などの棒を4本刺して、それぞれ牛と馬に見立てて飾ります。どちらも先祖があの世とこの世を行き来するために使う乗り物です。一般的には「キュウリの馬で早くこの世へと帰り、ナスの牛でゆっくりあの世まで戻ってほしい」という願いが込められています。地域によっては逆の意味合いで用いられる場合もあるようです。ナスとキュウリが用いられる理由は諸説ありますが、有力な説として「どちらもお盆の時期が旬で調達しやすかったため」というものがあります。
精霊馬は一般的なお供え物でなく先祖を運ぶ乗り物のため、お盆が終わっても食べずに塩で清めてから可燃ごみに出して処分しましょう。真夏に棒で穴をあけて常温保存する形のため、衛生面でも食べるべきではありません。
お盆とハロウィンの共通点・違い
お盆はインドから東洋に広まった行事ですが、西洋でも近い内容の行事としてハロウィンが行われています。
ハロウィンは古代のヨーロッパに広く住んでいたケルト人の祭が起源とされます。当時のケルト人は仏教のような輪廻転生を信じており、ケルト人の暦で大晦日にあたる10月31日に亡くなった人が帰ってくると考えていました。お盆と異なり先祖だけでなく悪霊も来るとされて、悪霊にさらわれないようにお化けの仮装をするようになったようです。
ハロウィンもお盆と同様にあの世から帰ってくる先祖を迎える目的があり、灯りを灯したり野菜で飾りを作ったりする点も共通しています。時期や各種の風習など異なる点も多くありますが、さまざまな共通点からハロウィンが「西洋のお盆」と呼ばれる場合も少なくありません。
お盆を迎える流れ
お盆はおおよそ4日間にわたって行われる行事であり、事前の準備も含めるとやるべきことが多く存在します。現代では簡易的に親族と会う程度で済まされる場合も多いものの、本格的な流れを知っておくと実際にお盆を過ごすうえで役立つかもしれません。本格的なお盆の流れを以下で紹介します。
事前の準備
お盆を迎える際は事前に複数の準備が必要です。必要な準備として主に以下のものが挙げられます。
・お寺に連絡する
お寺に法要を依頼する場合は極力早めに連絡しましょう。お盆は法要の需要が非常に高くなるため、ギリギリに連絡してもお寺側のスケジュールに余裕がありません。特に四十九日の忌明け後最初に迎える「新盆」では要注意です。通常のお盆より規模が大きくなりやすいため、新盆を迎える際は早め早めに準備しましょう。
・仏壇とお墓を掃除する
先祖を迎える前に仏壇やお墓をきれいに掃除しておきましょう。帰ってくる先祖のためだけでなく、集まってきた親族が気持ちよくお参りするためにも重要です。仏壇のホコリや墓石の汚れを落とすだけでなく、香炉の灰をきれいにしたり墓石周辺の雑草を取り除いたりと広範囲を掃除します。
・盆棚を用意する
お盆のお供え物を置く「盆棚」を用意しておきます。「精霊棚」と呼ばれる場合もあり、設置場所も仏壇の前や玄関などさまざまです。本格的に行う場合はマコモで作られた敷物やしめ縄などが必要ですが、簡易的なものとして机上にお供え物を置くだけでも問題ありません。精霊馬を作った場合はお供え物と一緒に盆棚へと置きましょう。
迎え盆
お盆の初日にあたる日を「迎え盆」と呼び、一般的には8月13日が該当します。日中にお墓参りしてから夕方に「迎え火」を灯しましょう。迎え火は先祖をしっかりと家に呼び込むための目印で、可能であれば墓前や玄関前に灯します。集合住宅ではベランダで行う場合もありますが、いずれの場所でも入居規約上問題ないか確認しておきましょう。火を灯せない家の場合は提灯を使います。通常のお盆では柄提灯を、新盆の場合は白提灯を灯しましょう。
先祖へのお供え物も迎え盆から本格的に供えます。基本的な内容は線香・花・食べ物など通常のお供え物と大きく変わりませんが、特に食べ物は普段より豪華なものが選ばれる場合も多くあります。
中日
お盆期間の中間にあたる日が「中日」で、一般的に8月14日と15日を指します。迎え盆と同様にお墓参りして、お寺から住職を招き読経してもらいます。その他、集まっている親族一同で会食も行いましょう。会食のタイミングに限らず、食べているものと同じ料理を1日3食供えます。精進料理のように肉や魚を使わないメニューで、食器にはお供え用の小さなものを使用しましょう。
中日の間は提灯を灯したままにしておく必要があります。少なくとも夜の家族が起きている間は提灯の灯りを消さず、室内を明るく保っておきましょう。
送り盆
お盆の最終日が「送り盆」と呼ばれる日で、一般的に8月16日が該当します。先祖があの世に戻る日ですが、午前中はこの世にいるため中日までと同様にお供えをしましょう。夕方が近づいたらお墓参りをしますが、霊園によっては夕方のお墓参りを受け付けていない場合もあるため要注意です。お墓参り終了後、暗くなったら「送り火」を灯します。迎え火と同じく墓前や玄関前に灯して、先祖が無事にあの世まで戻れるよう見送ります。
送り盆が終わったら飾りやお供え物などを片付けてお盆の行事は終了です。片付けのタイミングは送り盆当日や翌日など地域によって異なります。
まとめ
お盆の歴史やイベント、迎える流れなどを紹介しました。夏の風物詩であるお盆には、昔から多くの人が先祖を想いつつ過ごしてきました。現代ではお盆休みとして連休を設けられる場合が多く、全国各地のイベントとあわせて行楽シーズンとしても知られています。親族とゆっくり過ごしたり旅行を楽しんだりと、それぞれの形でお盆を迎えられるでしょう。本格的な形でお盆を迎える場合はさまざまな用意が必要です。
お盆をどのような形で過ごすにせよ、事前に準備や計画はしっかりと行っておきましょう。全国で多くの人が移動するタイミングであり、真夏の非常に暑い時期でもあります。余裕を持った状態でお盆を迎えて、心身をより効果的にリフレッシュさせてみてください。