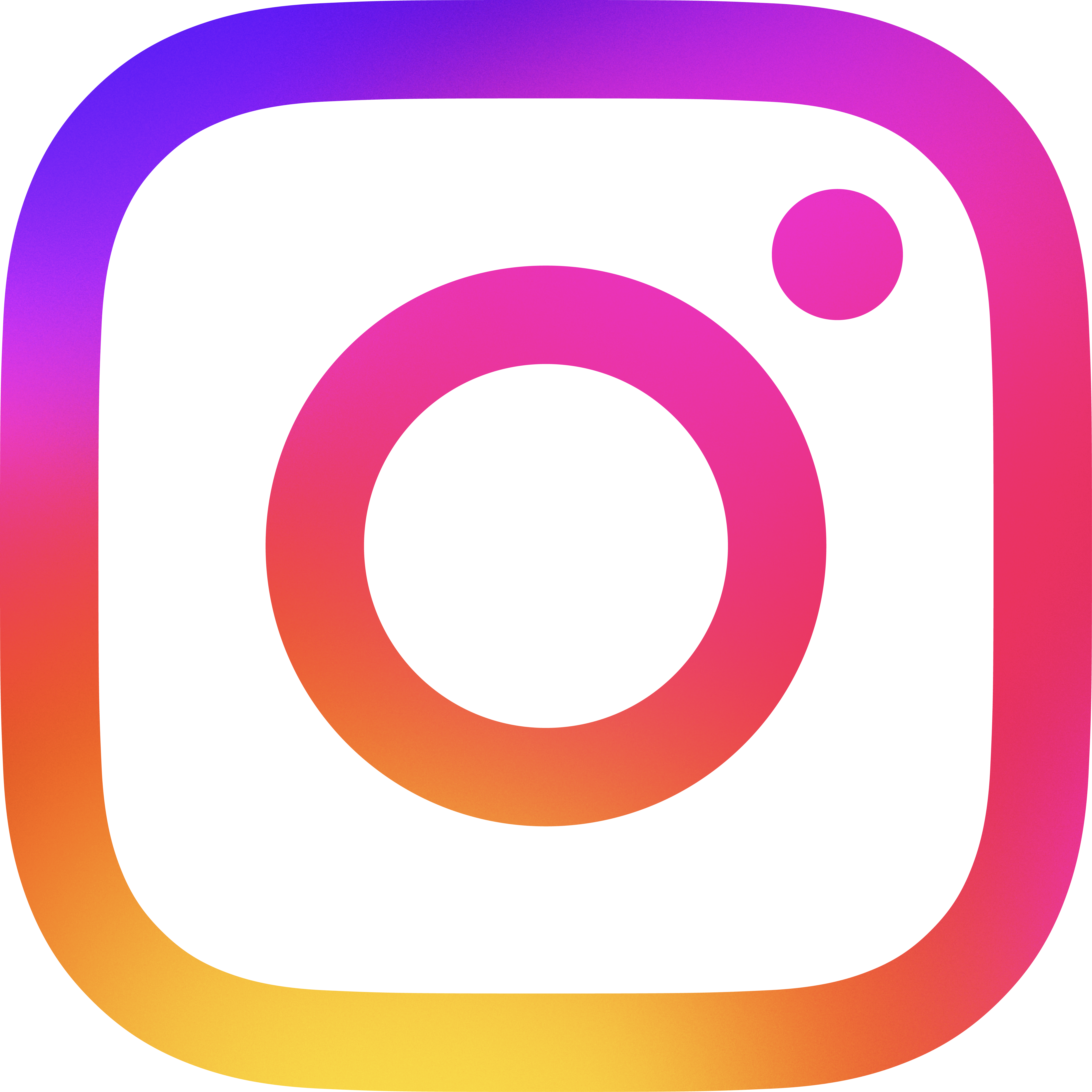秋の味覚・サケについて紹介!身近な美味しい魚のことを詳しく知ろう!

人間は古代から食材として非常に多くの生き物を活用してきました。野菜・穀物や動物に加えて、水場の近くを中心に魚も多く食べられてきています。
食材として活用されてきた魚として、日本やヨーロッパなどではサケも該当します。サケは毎年秋に同じ川で獲れる美味しい魚であり、今も昔も食卓に欠かせない存在です。身近な食材として活用されているサケのことを詳しく知ってみましょう。この記事ではサケについて概要や種類、料理方法など紹介します。
サケとは
サケは世界各地の川や海に生息する魚で、日本では北海道や東北地方を中心にみられます。「川で生まれて海で成長してから川に戻り産卵する」という生態が有名で、産卵のために戻ってきたサケは秋の味覚として人気の食材です。古くから幅広く活用されてきた魚で、現在でも美味しさや豊富な栄養素などから多くの注目を集めています。サケについて以下で詳しく解説します。
名前の由来
「サケ」という名前の由来には複数の説が存在しており、主に以下の3つが挙げられます。
・身が裂けやすいため
サケの身は筋があるため裂けやすく、この特徴から名づけられた説です。成長過程で胸腹が裂けることや産卵時に腹が裂けることなどに由来する説も存在します。
・身の色が赤いため
赤みを帯びた身の色から「朱(あけ)」と呼ばれて、「サケ」に転訛したという説です。酒に酔ったような色から「酒気(さかけ)」に由来する説も存在します。
・アイヌ語から伝わったため
アイヌ語の「シャケンベ(夏の食べ物)」が日本語に伝わって「サケ」になった説です。サケ漁が盛んだったアイヌとの交易で名前も広まったと考えられます。
サケを指して「シャケ」と呼ぶ人も少なくありませんが、どちらの呼び方も正解とされています。「江戸の方言でシャケと呼ばれていた」「食材としてのサケをシャケと呼んだ」など複数の説がありますが、正確な由来は判明していません。
参照:サケ/鮭/さけ | 語源由来辞典
鮭の呼び名は「シャケ」?「サケ」? | ウェザーニュース
「サケ」と「シャケ」どちらがよい?調査結果も | NHK放送文化研究所
生態
サケは川で生まれて海で育ち、川に戻ってきて産卵する生態があります。
日本に生息するシロザケは冬に生まれて、春まで川底でひっそり暮らします。春になると海に出て、北東のオホーツク海やベーリング海に向かいます。その後アラスカ近海まで泳いでいき、ベーリング海と往復しながら成長します。
海で数年過ごして大きく成長すると、産卵のために生まれた川まで戻ってくる「母川回帰」を行います。別の川に迷い込まず正しく帰れる理由として「匂いを覚えている」「地磁気から方角を判断している」などさまざまな説が存在しますが、詳しくは解明されていません。
生まれた川を遡上してきたサケは川底に穴を掘って産卵します。穴掘りはメスが行い、オスは外敵やほかのオスが近寄らないよう守ります。産卵を終えると大人のサケは死に、次世代にバトンをつなぎます。
参照:サケの生態 | マルハニチロサーモンミュージアム
自然の中でのサケの一生 | 北海道開発局帯広開発建設部
利用方法
サケは古くから世界各地で幅広く利用されてきました。ヨーロッパでは旧石器時代から、日本でも縄文時代にはサケ漁が行われています。サケは栄養豊富で大きな魚であり、毎年決まった時期・場所で多く獲れるため食料として重宝されてきました。獲ったサケは現地で食べるだけでなく、租税としても活用されていたようです。
サケが多く獲れる北海道においては、アイヌ民族から「カムイチェプ(神の魚)」と呼ばれて大いに活用されてきました。身や卵に加えてヒレや目玉なども残さず食べて、食用以外にも皮で靴や帽子などを作っています。
現代でも、サケは世界中で食用を中心に多く利用されています。2023年のサケ・マス類漁獲量・生産量はノルウェーが約163tで最も多く、以下チリ・ロシアと続いていました。世界的にメジャーな食材として、サケは多くの人の健康を支えてくれています。
参照:鮭と鱒の話 | 奈良文化財研究所
サケ漁の歴史 | マルハニチロサーモンミュージアム
千歳アイヌのサケ文化 | サケのふるさと 千歳水族館
2023年 サケ・マス類の漁獲量・生産量 | GLOBAL NOTE
栄養素
サケはさまざまな栄養素を豊富に含んでおり、健康な体を維持するために活躍してくれます。サケに多く含まれる主な栄養素として以下のものが挙げられます。
・タンパク質
体の維持に欠かせない各種の必須アミノ酸を豊富に含んでいます。牛肉や豚肉よりヘルシーなため、カロリーを抑えつつタンパク質の補給が可能です。
・EPA(エイコサペンタエン酸)・DHA(ドコサヘキサエン酸)
必須脂肪酸に含まれる栄養素で、中性脂肪や悪玉コレステロールを減らしてくれます。生活習慣病の予防に役立つほか、子供の脳発達や認知症予防などにも効果があるとされます。
・アスタキサンチン
赤い色を作る天然の色素で、身や卵の赤色を生み出しています。抗酸化作用が高く、老化の防止や疲労回復などに役立ちます。
・ビタミン類
各種ビタミンも豊富に含まれており、特にビタミンB群を多く摂取できます。糖質の分解や脂質の代謝など多くの役割があり、免疫やホルモンなど幅広い要素の健康維持に欠かせません。
参照:サケの栄養 | マルハニチロサーモンミュージアム
秋鮭・いくらの栄養 | 北海道ぎょれん
サケは白身魚?
サケの身は淡い赤色が特徴的ですが、マグロやカツオのような赤身魚でなく白身魚に分類されます。赤身魚・白身魚の分類は身に含まれるヘモグロビンやミオグロビンなど色素タンパク質の量で定められています。身100gあたりに10mg以上色素タンパク質が含まれていれば赤身魚です。サケの身に色素タンパク質はあまり含まれていないため、見た目が赤くとも白身魚として扱われます。サケは赤い色素のアスタキサンチンを多く含むエビやカニなどを食べて育つため、体内に色素が溜まって赤い身を持つようになります。
色素タンパク質を多く含む赤身魚は長距離を回遊する魚が中心です。色素タンパク質は筋肉内で酸素を蓄える作用があるため、長時間泳ぎ続けるために役立ちます。マグロやカツオに加えて、広範囲を回遊するブリやサンマなども赤身魚に含まれます。一方白身魚は長時間の遊泳が苦手ですが、瞬発的な動きを得意とします。天敵から逃れたり獲物を待ち伏せしたりと、ここぞというタイミングで素早く動く魚が対象です。サケだけでなく、タラ・ヒラメ・フグなどが白身魚として有名な例でしょう。
参照:赤身魚と白身魚の違い そして・・・青魚と赤魚とは?? | 魚食普及推進センター
「赤身?白身?」 | 新潟県立自然科学館
サケとマスの違い
サケと近い魚としてマスが挙げられます。どちらも身や卵を中心に食材として多く利用されていますが、サケとマスを区別するはっきりした違いはありません。傾向として「海に出るものがサケ、一生を川で過ごすものがマス」という区分は存在します。しかし、生態がよくわかっていない時期に名づけられたため区分にあてはまらない種類も少なくありません。日本に限らず、英語でもsalmon(サケ)とtrout(マス)の区別はあいまいな基準です。
サケとマスははっきりした違いがありませんが、個々の種類では原則としてどちらかに分類されています。国産のサケは一般的に在来種のシロザケで、ノルウェー産のものも多くは養殖されたアトランティックサーモンです。一方、一般的なマスとしては在来種のサクラマスや北米原産のニジマスなどが挙げられます。
参照:鮭、鱒、サーモン、トラウトの違い | 魚食普及推進センター
イクラと筋子の違い
サケは身だけでなく卵も「イクラ」や「筋子」と呼ばれて人気の食材になっています。イクラはロシア語で「魚卵」「粒々したもの」などの意味を持つ単語で、筋子は卵が筋状につながっているさまから名づけられています。
イクラと筋子はどちらもサケの卵ですが、筋子は卵が卵巣膜に包まれてまとまっています。筋子の卵巣膜を取り除いて卵同士をバラバラにするとイクラになります。同じサケの卵を2種類の形で扱う理由として、獲った時点での卵の成長度合いの違いが挙げられます。イクラにできる卵は大きく成長しており、皮も弾力があります。一方未成熟の小さな卵はバラバラにできないため、まとまったまま筋子として扱われます。
イクラと筋子は味付けの方法も異なります。イクラは醤油漬けが一般的ですが、筋子は塩漬けが多く用いられます。味付けと食感の違いにより異なる形で楽しめるため、ぜひイクラと筋子を食べ比べてみましょう。
参照:そもそもスジコとイクラの違いは? | 魚食普及推進センター
サケの種類
サケの仲間は世界各地に多数存在しており、それぞれ異なる特徴を持っています。日本において比較的身近なサケとして、主に以下の種類が挙げられます。
・シロザケ
日本に生息する一般的なサケで、秋鮭や秋味などと呼ばれる場合もあります。日本で生まれたシロザケは北太平洋をアラスカ周辺まで泳いでいき、産卵のために日本まで戻ってきます。ほかのサケと比べて身の色が薄く、脂が控えめでさっぱりしている種類です。
・ベニザケ
主にオホーツク海からアラスカにかけて生息するサケで、産卵の時期を迎えると体色が美しい赤色に変わる特徴があります。体色だけでなく身の色も赤みが濃く、ほどよい脂と濃厚な味わいが魅力です。
・ギンザケ
オホーツク海や北米に生息するサケで、一般的にはチリで養殖されたものが流通しています。産卵直前のシロザケも「ギンザケ」と呼ばれる場合がありますが、こちらは普段から銀色の体を持つ別種です。身は柔らかく脂がよくのっています。
・キングサーモン
オホーツク海や北米などに生息する大型のサケです。日本でもまれに獲れる場合があり、「マスノスケ」と呼ばれています。体が大きいため身もほかのサケより厚みがあり、脂も多く含んでいます。
・アトランティックサーモン
ヨーロッパや北米沿岸など大西洋に生息するサケです。ノルウェーを中心に多数養殖されており、日本でも単に「サーモン」と呼ばれて広く流通しています。身は淡いオレンジ色で、脂が多く甘みのある味わいを楽しめます。
・サーモントラウト
北米原産のニジマスを海水で養殖したもので、「トラウトサーモン」と呼ばれる場合もあります。川から海に下って生活するニジマスは「スチールヘッド」と呼ばれます。鮮やかなオレンジ色の身を持ち、さっぱりした味わいや弾力のある歯ごたえが特徴です。
・時鮭・鮭児(トキシラズ・ケイジ)
どちらもシロザケの若い個体で、独立した種類ではありません。時鮭は春から初夏に獲れる産卵準備ができていないサケで、一般的な秋のシロザケより脂を豊富に含んでいます。鮭児は成長しきっていないサケが産卵するサケの群れに混じった希少なもので、非常に脂ののりがよく美味しいサケとして知られます。
サケ・イクラを使った料理
サケは古くから世界中で食材として活用されてきており、現代でも卵であるイクラとあわせて多くの料理に用いられています。一般的なものから珍しい郷土料理まで、サケは多くの形で食卓を彩ってくれるでしょう。サケ・イクラを使う料理の例を以下で複数紹介します。
・サケの塩焼き
サケの切り身に軽く塩を振って焼いた料理です。サケの一般的な調理方法で、特に家庭でのサケ料理として非常に多く提供されます。ふっくらした身や香ばしい皮などを同時に楽しめます。
・サケのムニエル
サケの切り身に薄く小麦粉をまぶして焼いた料理です。小麦粉でサケの旨みを閉じ込める効果があり、バターを使って焼けばさらに豊かな風味も楽しめます。レモンを添えて爽やかな味わいにする場合もあります。
・サケのホイル焼き
サケの切り身を野菜やキノコなどと一緒にアルミホイルで包んで焼く料理です。食材の水分を生かして蒸し焼きにするため、ふっくらした食感が楽しめます。サケと野菜を軽く焼いてから包むと旨みをより多く閉じ込められます。
・ちゃんちゃん焼き
サケと野菜を蒸し焼きにして味噌で味を付けた料理です。北海道石狩地方の漁師が発明したとされており、現在でも北海道の郷土料理として知られています。手軽に作れて栄養バランスもよいため、北海道だけでなく全国的に一般的なサケ料理として広まっています。
・石狩鍋
サケのぶつ切りやあらを野菜と一緒に煮込んで味噌で味付けした料理です。ちゃんちゃん焼きと同様に、石狩地方の漁師から全国に広まりました。最初は獲れたばかりのサケを味噌汁の鍋に入れていたとされます。
・ルイベ
冷凍したサケを凍ったまま刺身のように薄切りにした料理です。アイヌ民族が冬の保存食として発明したとされており、名前もアイヌ語の「ル(溶ける)」+「イペ(食料)」が由来です。サケとイクラの醤油漬けを冷凍した「ルイベ漬け」も人気があります。
・ぼだっこ
ベニザケを塩漬けにした料理です。秋田県の郷土料理で、一般的な塩鮭と比べて多くの塩を使う特徴があります。味は非常に塩辛く、焼くと塩が噴き出してくるほどとされます。「一切れのサケでご飯をたくさん食べられる」料理として話題を集めています。
・はらこ飯
丼に盛った炊き込みご飯にサケとイクラを乗せた料理です。宮城県亘理町で生まれた郷土料理で、阿武隈川沿いに住む漁師が発明しました。地域の家庭で作られるだけでなく、県内各地の飲食店や秋祭りの会場などでも提供されています。
・太宰丼
丼に盛ったご飯に納豆と筋子を乗せた料理です。納豆には醤油やタレをかけず、筋子の塩分で味を付けます。作家・太宰治の好物であったとされており、現在では青森県津軽地方の飲食店で提供されています。
サケを観られる施設
日本人の食生活に欠かせない存在のサケですが、生息地が限られている点もあり生きている状態で見られる機会は多くありません。サケを一層身近に感じられるように、サケの生体を観られる施設に行ってみましょう。多くの施設は北海道にありますが、施設によっては道外にも存在します。サケを観られる主な施設を以下で紹介します。
サケのふるさと千歳水族館
北海道千歳市にある施設で、淡水としては日本最大級の水槽を設けています。サケだけでなく北海道内や世界各地の淡水魚を多数展示しているほか、エサやりやサケの稚魚放流など体験も楽しめます。隣に設けられている道の駅「サーモンパーク千歳」とあわせて、サケをさまざまな形で学習・満喫できるでしょう。
所在地:北海道千歳市花園2丁目312
アクセス:JR千歳駅より徒歩約14分
参照:サケのふるさと千歳水族館公式サイト
道の駅「サーモンパーク千歳」公式サイト
標津サーモン科学館
北海道標津町にある施設で、シロザケを中心にサケ科の魚類を多数展示しています。サケのライフサイクルにあわせて展示内容を変えている「魚道水槽」が特徴的で、秋にはサケの産卵を観られるかもしれません。地上30mから知床半島や根釧原野などを見渡せる展望室も設けられており、標津の雄大な自然を楽しめます。
所在地:北海道標津郡標津町北1条西6丁目1-1-1
アクセス:中標津バスターミナルよりバスで約36分、サーモンパーク入口停留所よりすぐ
札幌市豊平川さけ科学館
北海道札幌市にある施設で、サケに関するさまざまな展示が行われています。サケの生体だけでなく剥製を用いたジオラマや実寸大模型なども展示されており、サケという生き物についてさまざまな知識を得られます。自然豊かな公園の敷地内にあり、付近の豊平川・真駒内川とあわせて美しい自然も同時に楽しめるでしょう。
所在地:北海道札幌市南区真駒内公園2-1
アクセス:札幌市営地下鉄真駒内駅よりバスで約6分、真駒内競技場前停留所より徒歩約4分
イヨボヤ会館
新潟県村上市にある施設で、「日本で最初の鮭の博物館」とされています。「イヨボヤ」はサケを意味する現地の方言で、サケの生態やサケにまつわる文化・歴史などを学べます。サケの塩引きづくりを体験できる点も特徴で、生のサケを切って塩引きまで行えます。仕上げ加工は自分で行うか代行してもらうか選択可能で、どちらも完成後に自宅の食卓で楽しめます。
所在地:新潟県村上市塩町13-34
アクセス:JR村上駅よりバスで約6分、イヨボヤ会館停留所よりすぐ
参照:イヨボヤ会館公式サイト
まとめ
サケについて概要や種類、料理方法など紹介しました。獲りやすく栄養豊富なサケは、古くから世界各地で食材を中心に活用されてきた魚です。現代でも多くの人の食生活を支えており、身近な美味しい魚として人気を集め続けています。サケに関するさまざまな知識を得られれば、サケの美味しさや栄養素などをより効果的に引き出せるでしょう。
サケは川から海に出て産卵のために川まで戻ってくる魚であり、川が汚れていると戻ってこられず産卵できません。サケが川からいなくなると周辺に生息する多くの生き物にも影響が生じます。サケや生き物たちを守れるように、川の環境保全や稚魚放流などについても調べてみましょう。