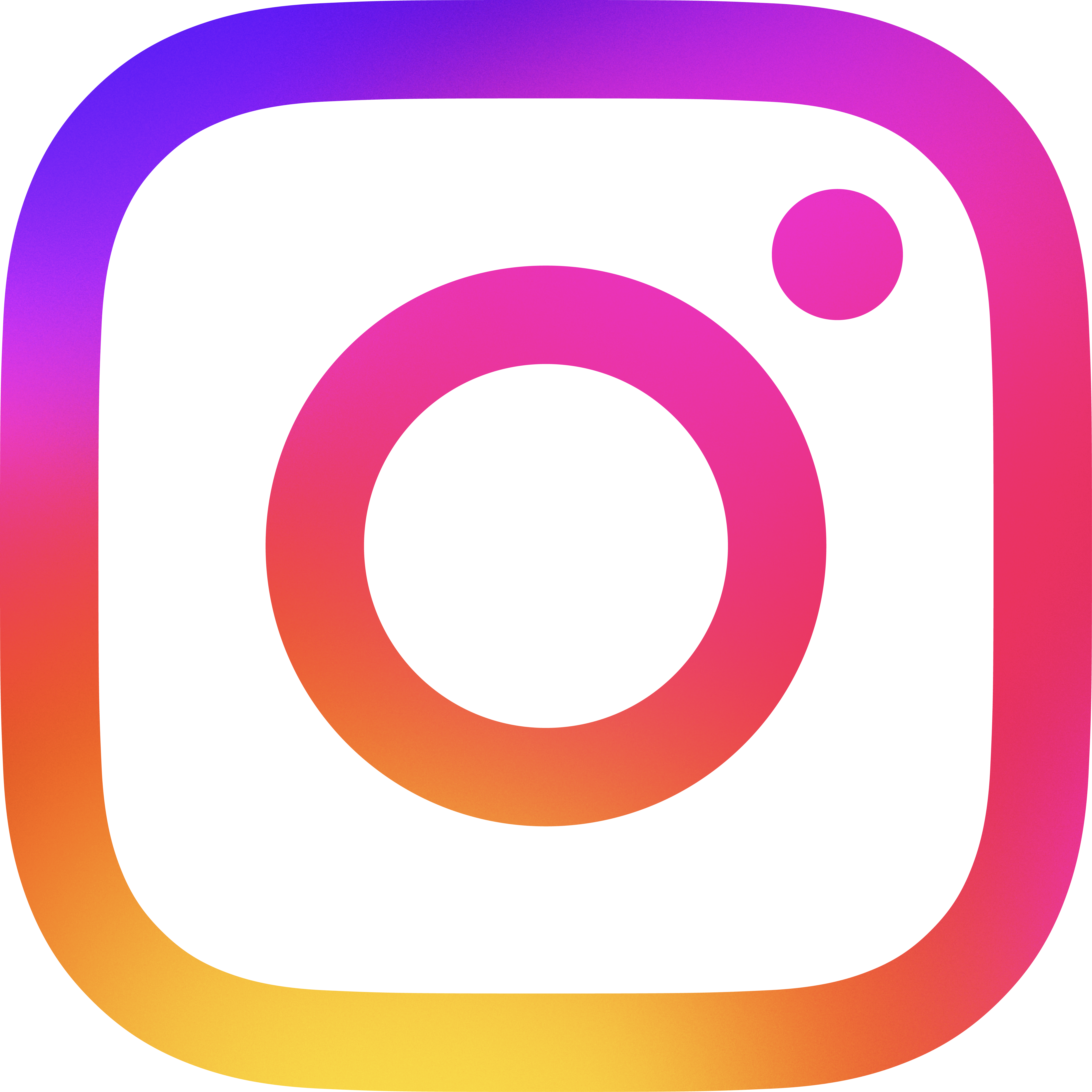新しく始まる就労選択支援って?内容をわかりやすく解説!

障害を持つ方が「自分に合った仕事を見つけたい!」と思っても、自分の能力を客観的に評価することが難しかったり、いろいろな選択肢の中からどれを選べば良いのか分からなかったりするケースが多いのが現状です。
そんな中、2025年10月から就労継続支援B型で先行して利用が開始されるのが「就労選択支援制度」です。この制度は、障害を持つ方が自分により適した働き方を見つけるためのものです。
この記事では、就労選択支援の詳しい内容や利用の流れなどについてわかりやすく解説します。
就労選択支援とは何か?その定義や目的について解説!
就労選択支援とは、わかりやすく言うとどういったものなのでしょうか。ここでは、その定義や目的などについて解説します。
就労選択支援の定義
就労選択支援について、厚生労働省は下記のように言及しています。
障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設する。
引用:就労選択支援に係る報酬・基準について≪論点等≫(厚生労働省)
アセスメントとは、「客観的に評価すること」を意味します。つまり、障害を持つ方本人の能力や適性を客観的に評価し、その人が自分により適した就労先・働き方を選び取ることができるよう支援することが就労選択支援のサービスだと言えます。
就労選択支援の目的
就労選択支援の目的について、厚生労働省は下記のように言及しています。
働く力と意欲のある障害者に対して、障害者本人が自分の働き方を考えることをサポート(考える機会の提供含む)するとともに、就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障害者には、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一般就労等への選択の機会を適切に提供する。
引用:就労選択支援に係る報酬・基準について≪論点等≫(厚生労働省)
つまり、現在就労継続支援などを利用している方もしていない方も、障害を持つ方が自分に合った働き方を見つけられることが就労選択支援の目的であると言えるでしょう。
就労選択支援の対象者や開始時期
就労選択支援は、就労系福祉サービスの利用を新たに希望する方だけでなく、就労系福祉サービスを既に利用中の方も対象者に含まれます。特に、就労継続支援A型やB型に関してはいったんそれらの利用が始まるとその状態が固定され、続いていってしまいやすいという現状があります。障害を持つ方が自分に合う働き方を見つけるためには今後就労選択支援が重要な役割を担うと言って良いでしょう。
就労選択支援は2025年10月から利用開始が予定されていますが、就労系福祉サービスを新たに利用したいと考えている人・既に利用している人によって、またはどの就労系福祉サービスを利用しているかによって就労選択支援の利用時期が違ってくるので注意が必要です。
参照:就労選択支援に係る報酬・基準について≪論点等≫(厚生労働省)
就労選択支援で具体的にどんなサービスが受けられるのか?
就労選択支援の定義や大まかな目的が分かったところで、今度はもう少し具体的に、就労選択支援でどんなサービスが受けられるのかを解説していきます。
アセスメントの実施とその結果の活用
障害を持つ方一人一人の強みや能力、特性などを客観的に評価し、本人と共に理解し整理します。それを踏まえた上で、本人が自分はどこで何ができるかを考えられるように支援します。そして、就労継続支援A型なのか、B型なのか、就労移行支援なのか、はたまた一般就労なのか、本人が自分の進路について選び、自分で決定できるように支援します。
ポイントは、就労選択支援を行う中で障害を持つ方が就労できるかできないかを支援者が一方的に判断したり、支援者が障害を持つ方の就労系福祉サービスの利用先を勝手に決めたりすることはないということです。あくまでも主役は「障害を持つ方本人」なのです。
情報提供や助言
障害を持つ方本人が自身の就労に関する選択肢を広げられるように、また納得のいく選択ができるように、地域の就労系福祉サービス事業所や一般企業についての情報を提供します。また、就労に関する相談に応じ、助言をします。
関係機関との連携など
就労選択支援事業所は、市町村やハローワークなどの関係機関と連絡調整を行い、適宜連携をとれるようにします。
就労選択支援の利用方法について解説!利用の流れはコレ!
就労選択支援を利用するには、どのような流れで手続きをしたら良いのでしょうか。ここでは、就労選択支援の利用の流れについてわかりやすく解説します。
1.利用申請の手続きを行う
障害を持つ方が市町村の相談支援センターに行き、就労選択支援の利用申請を行う。就労系福祉サービスの利用を希望するかどうかや心身の状態について利用者本人が担当者に伝える。その後、サービスの支給が決定される。
2.アセスメントの実施
就労選択支援事業所にて、支援者がアセスメントを実施する。作業場面などを通じて利用者本人の能力や特性を支援者が把握し、評価する。
3.ケース会議の実施
就労選択支援事業所が市町村やハローワーク、医療機関などの関係機関と連携し、アセスメントの結果をもとにしてケース会議を行う。
4.アセスメントの結果を利用者や家族と共有する
支援者がアセスメントの結果を利用者や家族に伝え、共有する。アセスメントの結果を踏まえた上で利用者が自己理解を深められるように、また利用者が自ら就労先を選べるようにサポートする。
5.関係機関との連絡調整
本人にとって適切な支援を行えるよう、関係機関と情報共有や連携を実施する。
6.利用者の就労先が決定
利用者の就労先が決定する。
参照:就労選択支援に係る報酬・基準について≪論点等≫(厚生労働省)
就労選択支援はどこがやる?こんな事業者が任される予定!
就労選択支援制度が新しく創設されたと言っても、その役割はどこが担うのでしょうか。ここでは、就労選択支援を行う事業者はどこなのかについて解説します。
就労選択支援を行う事業者はこんなところ!
就労選択支援を行うにあたって、実施主体に求められるのは下記の2点です。
- 障害を持つ方の就労支援に関し一定の経験と実績を有している。
- 地域における、就労支援機関などの状況や企業などの障害者雇用の状況を利用者へ適切に情報提供することが可能である。
この2つを満たす事業者とはどんなところなのでしょうか。厚生労働省は例として下記のような事業者を挙げています。
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所
- 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
- 自治体設置の就労支援センター
- 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関
- これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県等が認める事業者など
これらの事業者が就労選択支援の実施主体となるには、過去3年間において3人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている必要があります。
このように、就労選択支援制度が新しく創設されるからと言って何か新しい事業所などが作られるというわけではなく、既存の事業者が就労選択支援の役割を「兼ねる」イメージなのだということが分かります。
新たに就労選択支援の要素をプラスするのがどこの事業者かによっても、就労選択支援の在り方が変わってきそうですね。
参照:就労選択支援に係る報酬・基準について≪論点等≫(厚生労働省)
就労選択支援をうまく利用して新たな一歩を踏み出そう
就労選択支援について解説してきました。就労選択支援を利用して自分の能力や特性を客観的に評価してもらうことで、自己理解が進み、進路を選びやすくなります。自分の感覚だけでなんとなく就労先を決めるということが無くなります。
すでに就労継続支援事業所などで働いている方も、就労選択支援を利用して定期的に自分の状況について助言を受けることが必要かもしれません。実は自分でも知らぬ間に成長していて、次のステップに行くことが可能になっているかもしれないからです。
障害を持つ方にとって就労選択支援は、自身を喜ばしい未来に繋ぐ大きな味方になってくれるに違いありません。就労選択支援のまだ見ぬ可能性に期待しましょう。