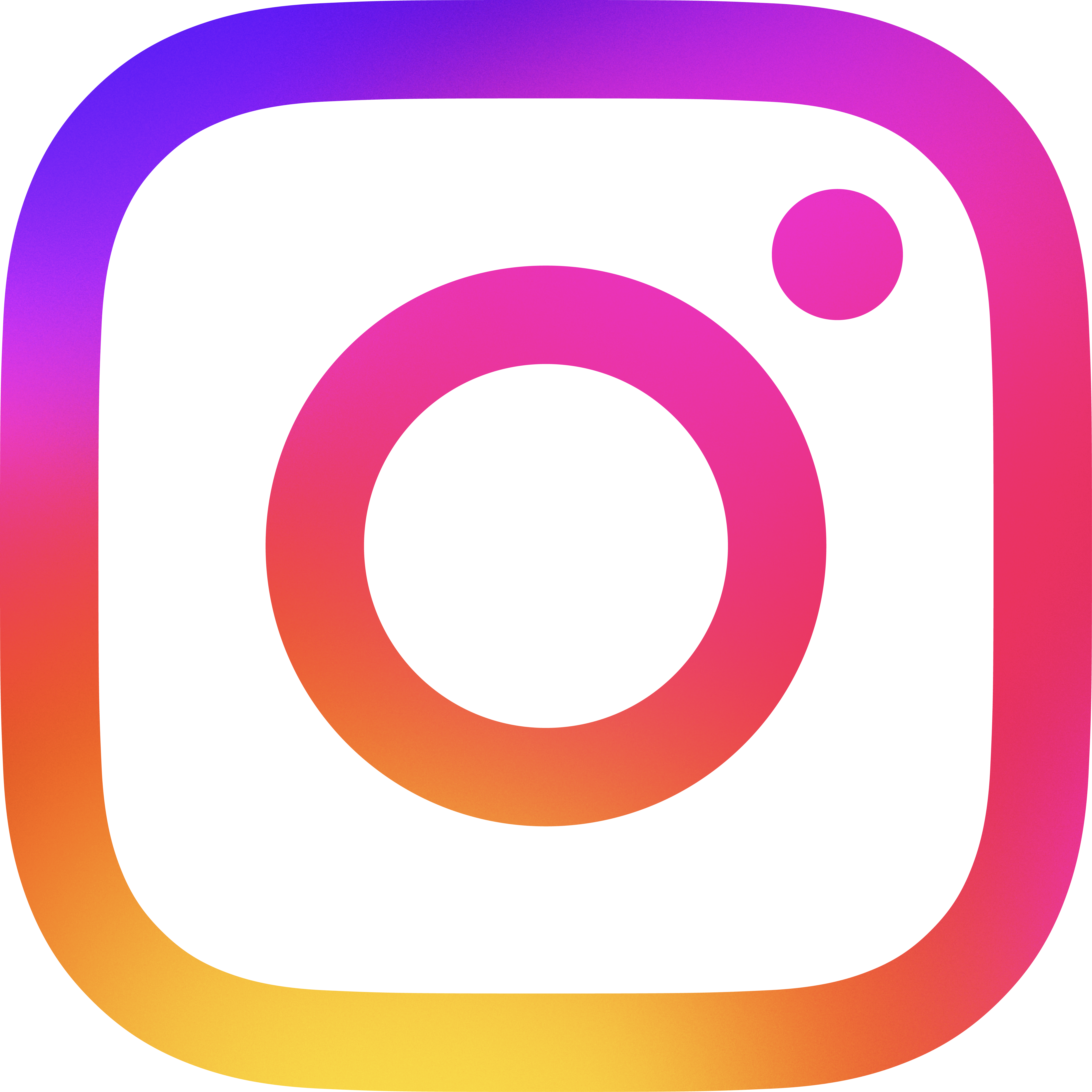大人のASDの特徴って?その生きづらさへのヒントを解説

「人付き合いが苦手」「なんとなく生きづらい」そう思いながら毎日を過ごしていませんか?それは性格の問題なのではなくて、もしかしたらASDの特性によるものである可能性があります。ここでは、大人のASDの特徴や対処法について解説していきます。
大人のASDとは何か?ADHDとの違いを分かりやすく解説
ASDって何?大人のASDってどういう意味?ADHDとの違いは?これらの疑問にお答えしながらASDについて解説していきます。
ASDとは
ASDは、Autism Spectrum Disorderの略で、日本語に訳すと「自閉スペクトラム症」となります。スペクトラムには「連続している」という意味があり、特性を「あるorない」ではなく「強いor弱い」という風に「連続体」として捉えようという姿勢を表しています。
ASDは発達障害の一つです。他人とコミュニケーションを図る場面で、例えば言葉・視線・表情・身振りなどによるやりとりが難しいという特性があります。
また、自分の気持ちを伝えたり、相手の気持ちを汲んだりすることも苦手です。
参照:自閉スペクトラム症(ASD)とは – 武田薬品工業 | 「大人の発達障害ナビ」
大人のASDとは
最近では、大人になってからASDと診断される人が増えてきたとも言われています。これは、多くの人が大人になってから急にASDになったということなのでしょうか。
答えはそうではなくて、元々ASDだった人が子どもの頃はASDだと気づかれなかったけれど、社会に出て円滑なコミュニケーションをとることを求められ、うまくできないことで「生きづらさ」を感じ、精神科を受診したらASDだった、というケースが多いからだと考えられます。
よって、大人のASDとは、その特性により社会的コミュニケーションなどの様々な行動パターンに対し困りごとを抱えている状態であると言えます。
ADHDとの違い
ADHDとは「注意欠如多動症」のことで、その特性は「不注意」と「多動性・衝動性」の2つに分けられます。ASDとは特性が異なるものの、目に見える表面上の困りごとは共通していることがあるので注意が必要です。
例えば、ASDにもADHDにも当てはまる「相手の話に集中できない」という困りごとがあったとします。ASDの場合、この困りごとの原因は「そもそも話題が自分の関心の範囲外だから」であると考えられます。一方で、ADHDの場合、「聞こうとしても集中力が保てず、話が頭に入らない」ことが原因として考えられます。
このように、一見同じように見える困りごとでも本質が全く違うことがあるので、医師が判断に迷う場面もあるようです。
参照:大人向け|ASD(自閉スペクトラム症)とは?特徴やセルフチェックなど解説【専門家監修】
※ADHDについては下記の記事で詳しく説明しています。
→大人のADHDの特徴って?特性との向き合い方について調査
大人のASDの特徴はどんなもの?大人ならではの困りごとは?
大人のASDの特徴、そして困りごとにはどんなものが挙げられるでしょうか。ここでは、この2点について解説していきます。
大人のASDの特徴
大人のASDの特徴についてまとめてみました。
●社会的コミュニケーションが困難
- 場の空気を読んだり、暗黙のルールを読み取ってうまく振舞ったりすることや、表情・声のトーン・身振りなどから相手の気持ちを汲むことが苦手。
- 冗談・皮肉・比喩が通じず、文字通りに受け取ってしまうことが多い。
- 人と目を合わせて話すことが難しい。
●強いこだわりを持ったり同じ行動パターンを繰り返したりする
- 特定の分野について強い興味があり、豊富な知識を持つ。
- ルーティンを大事にし、手順の通り物事をこなす。
- 予定が急に変更されると不安や混乱を強く感じる。
- マルチタスクが苦手。
●感覚が過敏・または鈍感である
- 「騒音」「まぶしい光」に強い不快感を覚える。
- 肌触りの良いものを触り続け、逆に苦手な肌触りの服は着られない。
- 痛みや温度変化に鈍感なため、体調不良や怪我に気づくことが難しい。
参照:大人のASD(自閉スペクトラム症)- 沢井製薬|大人の神経発達症(発達障害).jp
ASDは個人差が大きいため、これらの特徴がすべてのASDの方に当てはまるというわけではありません。ADHDなどの特性を併せ持つことも多々あります。このように、その人がASDかどうかを判断するのはとても難しいことであると言えます。
大人のASDの困りごと
次に、ASDの特性により発生する大人ならではの困りごとをまとめてみました。
●組織に馴染めない
空気が読めない、相手の気持ちを汲むことが苦手だというASDの特性により、仕事をする上で必要になってくる円滑なコミュニケーションが成り立ちにくいです。
結果、会社という組織に馴染めず孤立してしまうことがあります。
●仕事に支障が出る
急に予定を変更されるとパニックになる、マルチタスクが苦手、職場の音やまぶしい光に不快感を覚えて仕事に集中できないなど、ASDの特性により仕事に支障が出てしまう時があります。
●二次障害の恐れも
以上のような困りごとにより、ASDの方が抱える悩みやトラブルが、過剰なストレスやうつ病や不安症など違う形のものとして現れることも。
これを二次障害と呼び、特に気をつけなければならない点です。
参照:大人のASDとの向き合い方とは?特徴と働きやすくするための工夫を解説 | 【公式】新宿うるおいこころのクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分]
これらの困りごとが「生きづらさ」に変わり、苦しみの中にいるASDの方は少なくないはずです。ではどうすればよいのでしょうか。
まずASDの特性に対する対処法を知ることが初めの一歩となります。
ASDの「生きづらさ」への対処法!大切なのは両者の歩み寄り
ASDの方にとって、たまたまここが令和の日本だから、この世界が「困りごとで溢れる世の中」なのであって、ASDの方が悪いとか劣っているというわけでは全く無いということを頭に入れておく必要があります。
しかし、令和の日本ではないどこか違う国や時代に行くというわけにもいかないので、ASDの方の「生きづらさ」を軽減するためにはASDの方と周りの方との歩み寄りが必要になってきます。
ここでは、ASDの方ができることと、周りの方ができることに分け、ASDの「生きづらさ」を軽減する方法を探っていきます。
ASDの方が自分でできる工夫
●仕事の場面でできること
- 自分専用のマニュアルを作る
- そのマニュアル通りに、少しずつ段階に分けながら進めていく
- スマホのアラームやカレンダー機能をうまく活用する
- 音や光が苦手なら、座席を調整したり、ノイズキャンセル機能があるイヤホン・光を遮るメガネなどを活用したりする
●医師と相談してできること
- 医師と相談し、必要なら薬物治療をすることも選択肢の一つに入れる
- 医師と相談し、必要ならソーシャルスキルトレーニングを受けることも選択肢の一つに入れる
アラームやイヤホン、メガネなどを使って環境調整をすることは比較的容易に試すことが可能なので、今より少しでも自分に合った環境へカスタマイズすることを検討してみましょう。
ソーシャルスキルトレーニングでは、例えばロールプレイにより周りの人とのトラブルを回避できる具体的な行動について学ぶことができます。
参照:
大人のASD(自閉スペクトラム症)- 沢井製薬|大人の神経発達症(発達障害).jp
発達障害関連ワード集 – 武田薬品工業 | 「大人の発達障害ナビ」
周りの方ができる工夫
●仕事の場面でサポートできること
- 急に指示を変更することを避ける
- 指示の内容を、曖昧なものから具体的なものに変える
- 視覚的な情報の方が分かりやすい人には、ホワイトボードに書いたり文書にして渡したりして伝える
- マルチタスクをお願いしないようにする
●日常生活の場面でサポートできること
- 自分の気持ちをしっかり言語化して伝えるようにする
- 人と話す時の定型文を用意し、一緒に練習する
- ルールや予定を明確にし、それが変更になったら早めに伝えるようにする
このように、少しだけ意識して接し方を変えるだけで、ASDの方との関係性が風通しの良いものになります。
この時、決して無理をしないことが大切です。無理をして関係を良くしようとしても周りの方が疲れてしまうので、無理なくASDの方に関われるような方法を探しましょう。
参照:大人の自閉症スペクトラム障害(ASD)との関わり方 | 川口メンタルクリニック
以上のようなことを、ASDの方と周りの方の両者が心がけるようにすれば、両者の間の溝は(少しだけかもしれませんが)埋まって、ASDの方の「生きづらさ」の軽減に繋がるという風に考えることができます。
ASDの特性は欠点ではない!「生きづらさ」を軽減して過ごそう
大人のASDは、その特性から職場や日常生活において様々な困りごとに直面することが多いです。
しかし、ASDの特性は欠点ではありません。やり方を変えれば、ASDの方ならではの得意な面を生かせることだって十分に可能なのです。
ASDの方と周りの方の両者がASDのことをよく理解し、お互いに話し合い、歩み寄ることによって、ASDの方の「生きづらさ」を今より少しだけ軽減できるかもしれません。
※本記事は、筆者が信頼できる情報源をもとに調査・執筆した内容です。医学的な判断が必要な場合は、必ず医師や専門機関にご相談ください。