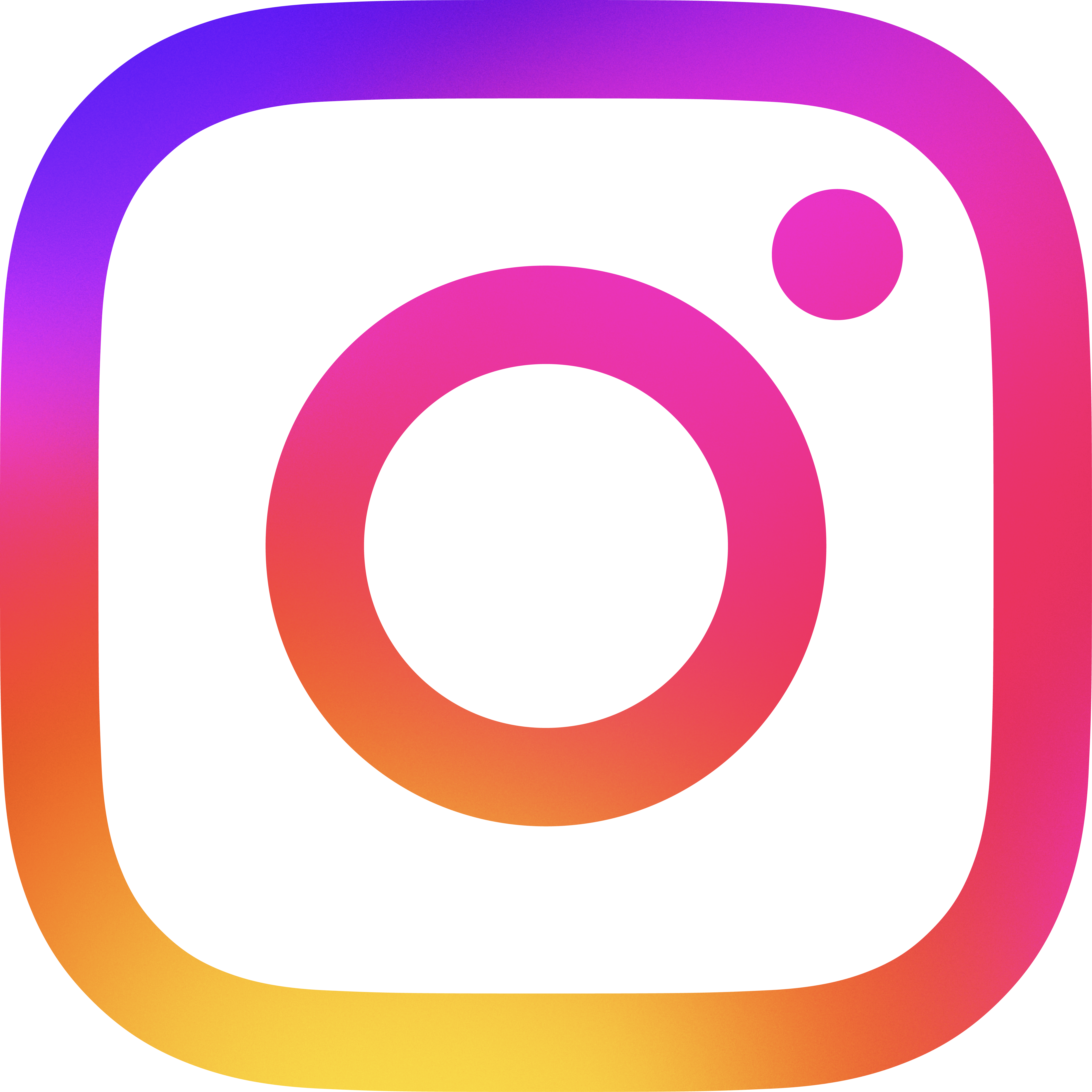インターネットで高齢者の安心・安全な生活を守れる見守りグッズとは?

高齢化が非常に進んでいる現代は、高齢者の割合が非常に多くなっている時代です。高齢者は急病やケガなどトラブルに見舞われるリスクが高く、本人や周囲の人が注意を払ったり迅速に対処したりしなくてはなりません。高齢者と同居していれば対応しやすい一方、高齢者が単身で暮らしているとなかなか対応できない可能性もあります。
高齢者が見舞われたトラブルにすぐ対応する手段として、インターネットを活用する各種の「見守りグッズ」が存在します。多くの人が日常的に活用しているインターネットで高齢者の生活を見守り、万が一に備えて安心・安全を確保できます。この記事では主に高齢者の安全を守る見守りグッズについて、選び方や例などを紹介します。
見守りグッズとは
見守りグッズとは、外出や別居などでその場にいない人物の安否を確認しやすくするグッズのことです。遅くまで塾に通う子供や一人暮らししている高齢者など、万が一トラブルが発生したときに深刻な事態を招く可能性は少なくありません。本人の安全や周囲の安心を確保するために見守りグッズが役立ちます。特に高齢化が進む現代では一人暮らしの高齢者が増加しており、自宅での急病やケガなどによるリスクを減らす必要性も増加しています。
高齢者の生活を見守る手段としては、警備会社や宅配業者などによる訪問サービスも存在します。人が家に直接訪問して安否確認できるため心強いサービスですが、大がかりな印象を与えたり多くのコストがかかったりする場合もあります。見守りを受ける高齢者と相談して、どのようなサービスが良いか決定しましょう。
見守りグッズの方式
見守りグッズにはさまざまな製品があり、主に4つの方式が用いられています。見守りたい高齢者の自宅に設置して使用するものが多く、様子を常に確認できるものや定期的な使用状況から確認するものが存在します。方式ごとにメリット・デメリットがあるため、対象の高齢者と周囲の人で意見をすり合わせてから導入しましょう。見守りグッズの主な方式を以下で詳しく解説します。
カメラ式
高齢者の自宅にカメラを設置して様子を確認する方式です。リアルタイムの様子を撮影して、主にスマートフォンアプリで映像を観られます。モデルによっては通話機能や音・気温などのセンサーが搭載されており、手軽にコミュニケーションをとったり異常をすぐに感知したりできます。
リアルタイムで状況を把握できるため、トラブルが発生した際に迅速な対応を行えます。一方で、高齢者にとっては常に撮影され続けるためストレスを感じる場合も少なくありません。カメラ式の見守りグッズを使用する場合は、ほかの方式以上に高齢者とよく話し合って承諾を得るようにしましょう。
センサー式
扉や照明など室内のさまざまな場所にセンサーを取り付ける方式です。扉の開閉や照明のオンオフでセンサーが反応する仕組みで、一定時間センサーが反応しない場合に登録した連絡先へと連絡が入ります。寝室やトイレなど毎日使う場所への設置が効果的です。センサーが反応していない=設置場所が使われていない点から、高齢者に発生したトラブルを察知できます。
カメラのように常時確認し続ける方式ではないため、ストレスを感じづらくプライバシーも保護できます。一方、トラブルの察知まで時間を要する可能性がある点に注意しましょう。センサーの種類や高齢者の生活リズムによってはうまく使用できない場合も考えられます。
スマート家電式
インターネットと接続できるスマート家電の機能を用いる方式です。スマート家電の多くはインターネット接続によってパソコンやスマートフォンとの連携が可能です。スマート家電の連携機能を生かして、高齢者による家電の使用状況をインターネット上で確認できます。電球・冷蔵庫・ポット・エアコンなど種類も多く、高齢者の好みや生活環境にあわせて選択できます。
高齢者自身はいつもと同じように過ごすだけでよいため、ストレスなく安心して生活できます。スマート家電の導入・設置にコストがかかる点には注意しましょう。特にエアコンは家の構造によって大がかりな工事が求められる場合もあります。
スマート家電についてはこちらの記事も参考にしてください。
ペンダント式
ペンダント型の端末を持ち歩き、トラブル発生時に本人の行動で通知する方式です。ボタン付きの端末を首にかけられるタイプが多く、ボタンを押すと登録している人にその場で連絡が入ります。急な体調不良や転倒などが発生したときにペンダントのボタンを押せば、すぐに助けを呼べるでしょう。持ち主自身のスマートフォンから大音量のアラームを鳴らせるモデルもあり、高齢者以外でも防犯ブザーとして活用できます。
ペンダントを携帯していればどこでもトラブルの発生を伝えられるため、室内に設置する方式以上に幅広く見守れます。特に入浴中でも使用できる点は大きなメリットでしょう。一方、常にペンダントを身につける必要があるため邪魔に感じられる可能性もあります。急に意識を失うようなケースには対応できない点にも注意しましょう。
見守りグッズの選び方
見守りグッズには多種多様なモデルがあり、それぞれ適している環境が異なります。ユーザーの環境と噛み合っていないグッズを選ぶと十分に活用できないかもしれません。グッズの利用目的や使いやすさなどを考慮して慎重に選びましょう。また、高齢者の見守りに使う場合は高齢者自身の意思が特に大切です。見守りグッズの選び方について以下で詳しく解説します。
高齢者自身の意思を聞く
高齢者向けの見守りグッズを導入する場合、何よりも見守られる高齢者自身の意思を尊重しましょう。見守りグッズは安心・安全を確保できる一方で高齢者を監視しているとも捉えられるため、人によっては不快感を覚える可能性があります。常時撮影し続けるカメラ式の見守りグッズは特に注意が必要です。可能であればグッズ選びの段階から高齢者自身も参加して、本人・周囲ともに納得して使えるものを選びましょう。疑問点の解決や不安感の解消を積極的に行うために綿密なコミュニケーションも欠かせません。
利用目的や高齢者の状況を考える
見守りグッズを選ぶ際には、グッズを使う目的や見守られる高齢者の状況などを考慮しましょう。グッズの種類によって様子を確認できる頻度や使える場所などが異なるため、目的や状況に合わないグッズを選ぶと十分な安心・安全を得られません。「常に欠かさず見守りたい」「ときおり安否確認できれば問題ない」など、見守りたい度合いを考えてからグッズ選択に進みましょう。
センサー式のグッズを選ぶ場合、特に高齢者の状況をよく考える必要があります。多くのグッズが高齢者の行動に応じて動作するため、普段使わないものや使えなくなったものにセンサーをつけても効果が得られません。問題なく使えるものや日常的に使っているものを探して、対応するグッズ選びにつなげましょう。
使いやすいものを選ぶ
見守りグッズは非常に多くのモデルが提供されているため、自身や高齢者が使いやすいと感じるものを選びましょう。使いづらく生活に不便なグッズを選ぶと、すぐにグッズを使わなくなったり余計なストレスを溜めてトラブルにつながったりするおそれがあります。普段の生活と噛み合って違和感なく使えるものを選び、長期間安定して見守れるように努めましょう。
使いやすさを考えるうえでコスト面の検討も重要です。便利なグッズでも導入コストやランニングコストが高いと利用しづらくなり、逆に安すぎるグッズでは十分に見守れない可能性が高まります。必要な機能と使える予算を照らし合わせて、問題なく使えるものを選びましょう。
主な見守りグッズ
見守りグッズは非常に多くのメーカーから多数提供されています。種類も多くそれぞれ強みを持っているため、高齢者や自分自身の意思・状況を考えて最適なグッズを選びましょう。グッズによっては初期費用が無料になる場合もあります。見守りグッズの例を以下で複数紹介します。
Echo Show
Amazon社が提供している見守りグッズで、便利な機能を楽しみつつ安心・安全も確保できるカメラ式グッズです。スピーカーにマイク・モニター・カメラなどが搭載されており、カメラ越しに外部から様子を確認したり顔を見ながら通話したりできます。高齢者の様子に不安を感じたら「大丈夫?」とすぐ呼びかけられます。
「Alexa(アレクサ)」というAIを使える点が大きな特徴で、「アレクサ、○○して」と口頭で指示するだけでさまざまな機能を活用できます。「ニュースを聞く」「音楽を流す」「動画を観る」など便利に使えるツールのため、高齢者を見守りつつ生活の利便性も向上させてくれるでしょう。
みまもりCUBE
ラムロック社が提供している見守りグッズで、手軽に幅広い場所で利用できるカメラ式グッズです。プラグをコンセントに差し込むだけで設置できて、複雑な手続きが必要ありません。SIMカードが内蔵されているためWi-Fi通信を使えない場所でも問題なく利用できます。センサーや呼び出しボタンの利用も可能なため、カメラ式以外の見守りグッズが持つ強みも同時に享受できるでしょう。
みまもりCUBEは30日間お試しでの利用も可能です。通常より安く利用できるため、使い心地を積極的に確認してみましょう。
ひとり暮らしのおまもり
日本ビジネス開発社が提供している見守りグッズで、低コストかつ簡単に利用できるセンサー式グッズです。テープで扉に貼り付ければ使用開始できるもので、一定期間扉が動かなかった場合に登録したスマートフォンへと通知が入ります。寝室・トイレ・冷蔵庫など毎日開け閉めする扉に貼り付ければ、万が一扉を開けられないようなトラブルが発生した際にすぐ対応できるでしょう。センサーに加えて、緊急通知ボタンとしても使える腕時計をオプションで付けられます。
ひとり暮らしのおまもりは買い切りで提供されており、月額料金が設けられていません。特に長期間利用したい場合はコストを大きく抑えられるでしょう。
いまイルモ
ソルクシーズ社が提供している見守りグッズで、高齢者のプライバシーを守りつつ日常的に見守れるセンサー式グッズです。気温や湿度・明るさ・動きなどを複数のセンサーで読み取って、カメラで撮影せずに日常生活の様子を把握できます。高齢者の状況を正確に把握できる安全性とカメラによる撮影を求められない安心感が両立されている見守りグッズです。設置も簡単に行えて、内臓のSIMカードによりWi-Fi通信も必要ありません。
センサーによる各情報は生活リズムの把握にも役立ちます。いまイルモから通知されるデータを高齢者に共有すれば、自主的な生活リズムの改善にもつなげられるかもしれません。高齢者と相談して活用してみましょう。
参照:いまイルモ公式サイト
ハローライト
ハローテクノロジーズ社が提供している見守りグッズで、安く充実したサポートを受けられるスマート家電式グッズです。IoT技術によって電球をインターネットに接続しており、設置した照明のオンオフを検知して見守ります。既存の電球を交換するだけで設置できて、料金も非常に安価なため気軽に利用できます。
ハローライトはヤマト運輸社によるサポートも提供されています。電球の設置やトラブル発生時の訪問などをヤマト運輸のスタッフが行ってくれるため、特に遠方で暮らす高齢者を見守る際に有用です。
参照:ハローライト公式サイト
クロネコ見守りサービス | ヤマト運輸
COCORO HOME
シャープ社が提供している見守りグッズで、高齢者や周囲の安心・安全だけでなく日常生活の利便性も向上させられるスマート家電式グッズです。IoT技術で家電とスマートフォンアプリを接続して、家電の使用状況から問題なく生活できているか確認できます。同社の冷蔵庫と空気清浄機が対応しており、「冷蔵庫の扉が開けられていない」のような状況からトラブルの発生を察知できます。
COCORO HOMEに含まれる家電は冷蔵庫と空気清浄機以外にも存在しており、さまざまな家電同士を連携させて幅広く活用できます。「料理中に洗濯完了を冷蔵庫から通知させる」「エアコンをスマートフォンで外出先から起動する」など、生活をより便利にしてくれるでしょう。
まとめ
主に高齢者の安全を守る見守りグッズについて、選び方や例などを紹介しました。カメラやセンサーなどとインターネットをあわせて見守り相手の状況を把握できるため、万が一のトラブルにすぐ対応できます。日常生活の安心・安全を確保できるでしょう。見守りグッズには非常に多くの種類が存在します。高齢者の意思や利用する状況などを考慮して、より適しているモデルを選びましょう。
見守りグッズで安心・安全を確保すると、万が一のトラブルをあまり恐れずに生活できます。日常の不安感を減らせればより元気に生活しやすく、ストレスの増加を防いでトラブル発生の可能性をさらに下げられるでしょう。トラブル発生に備えるだけでなくトラブル自体への防止策としても、見守りグッズの活用を検討してみてください。